スポット対応でする手続きや、自分の専門サービスだけを
受注したい人には使えません。
あくまでも、顧客の事業承継というイベントをマネジメントし、全体最適を作り出す
「コンサルティング」を提供したい人が対象です。
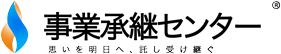
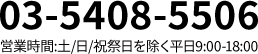 メール
お申込みi
メール
お申込みi
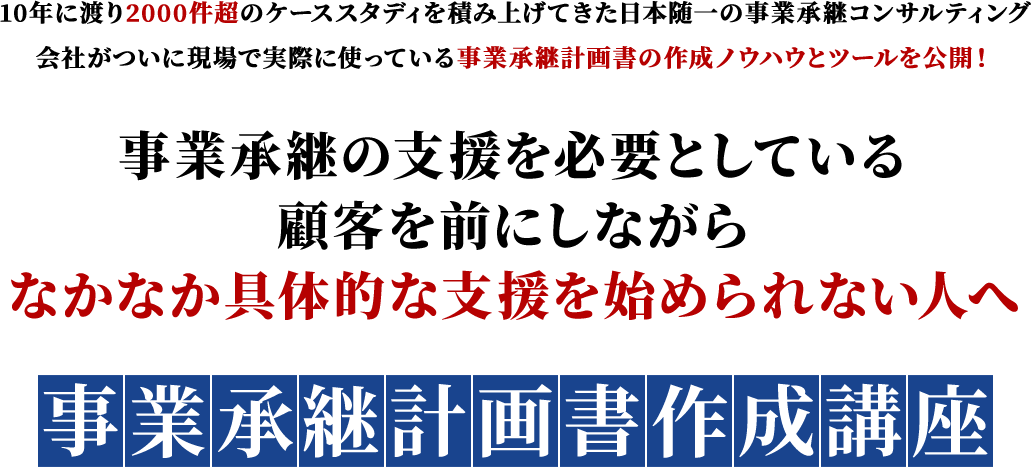
現役の実務家が実際に事業承継コンサルの現場で使っているツールを、
編集可能なデータで提供してくれ、具体的な事例に当てはめながら
使い方まで丁寧に教えてくれるチャンスを手にしたい士業・コンサルの方は
他にいませんか?
※当初、2023年度中に受講料の値上げを検討しておりましたが、皆様からのご意見・ご要望を受けまして、受講料の値上げについては当面見送ることと致しました。
この講座は、事業承継への道筋をたて、経営者が社長交代を決意するきっかけ作りになるだけでなく、経営者と後継者の対話を促進させ、事業承継の取り組みを後押しする『事業承継計画書』を作成する方法をお伝えするものです。
さらに、事業承継に関わる専門家サービスやコンサルティング契約に繋ぐための秘訣も分かります。
しかしこれは、全ての人が使えるものではありません。
この講座は少なくとも1日(8時間)、みなさんの貴重な時間を費やして受講して頂きますので、「こんなはずではなかった」という悲劇が起こらない為に、どんな人に使えないのかお話しします。
あくまでも、顧客の事業承継というイベントをマネジメントし、全体最適を作り出す
「コンサルティング」を提供したい人が対象です。
経営者と後継者の思いをヒアリングする為にコミュニケーションが最重要であるだけでなく、事業承継支援は他の専門家との連携が欠かせないサービスだからです。もちろん、全てのコンサルティングを自分一人で完結する必要はありません。他の専門家と協力して遂行するのが最適です。
例えば、お客様にとっての本質的な問題解決をコンサルタント として提供したいと思っている事業承継士・中小企業診断士・FP(ファイナンシャルプランナー)・税理士・行政書士・公認会計士・社会保険労務士や、金融機関・行政職員や保険募集人に向いています。

事業承継センター株式会社は事業承継に特化した経営コンサルティング会社として、長年にわたって中小企業の事業承継を支援するだけでなく、事業承継の専門家を養成する「事業承継士資格取得講座(開講5年半・受講者868名)」「事業承継プランナー資格取得講座(開講2年半・受講者609名)」を運営し、一般社団法人事業承継協会の活動を通じてこれらの講座から生まれた事業承継士・ 事業承継プランナーの知識の補充や活動の支援を行ってくる中で、共通の悩みがあることに気が付きました。それは事業承継対策が必要なのは明らかなのに、経営者が認識していない、気付いていない、危機感がない、ため支援が進まないというものです。つまり、
事業承継をテーマにした面談の機会をなかなか作れていない
という状態です。せっかく時間をかけて事業承継に関する知識を学び、様々な事業承継のテクニックを習得しても、それを使う機会がないのです。正に「宝の持ち腐れ」です。
それでも、“世はまさに、大事業承継時代!” 。日本には事業承継対策が必要な企業がたくさんありますので、事業承継という看板を掲げて顧客対応をしていれば、その内に事業承継に取り組まねばならない企業と出会うこともあります。
ですが、やっとのことで見込客と商談の機会を得ても、
成果物として提示できる定型物がなく、経営者に事業承継を
イメージしてもらいにくいため、効果的な提案ができない・・・
という問題が立ちはだかります。
ただでさえ複雑でテーマが多岐にわたる事業承継なのに、全体像が分からないため経営者が迷ってしまい、取り組みに着手する決断を促すことが、とても難しいのです。また、そのことが、税理士・司法書士・行政書士・不動産鑑定士など、事業承継における手続き・契約をスポットで支援する専門家にとっても、事業承継の全体最適の為のコンサルティングサービスを有償で受託しにくい、という状況を作り出しています。ひと言で言うと、
事業承継というコンテンツの価値を伝えるのが難しい
のです。これらの障害を乗り越え、ようやく事業承継支援コンサルティングを受託しても、悩みはさらに続きます。
『コンサルフィーをもらって事業承継支援を受託したが、手探り状態で自信が無い。』
『見栄えのいいアウトプットフォーマットがないため、顧客が満足してくれるか(クレームにならないか)不安だ・・・。』などなど・・・。事業承継コンサルタントの悩みは尽きないのです。
なぜ、既に事業承継について十分な知識を学んだ専門家が、さらにこの講座を受講しているのでしょうか?
『事業承継で発生する個々の問題を専門家として解決できる』ということと、『事業承継の取り組みの必要性や価値を感じてもらい、事業承継に着手してもらう』ということは全くの別物です。だからこそ、既に十分な知識のある事業承継士・事業承継プランナーが、この講座を受講しているのです。
『納得して事業承継に着手してほしい』
『しかも、自分が専門家として支援しながら』
私たち事業承継センター株式会社は、設立から一貫して事業承継コンサルティングに取り組んできました。事業承継の専門家として、これらの悩みを持ちながら、川崎信用金庫・多摩信用金庫・平塚信用金庫・横浜信用金庫・東京海上日動あんしん生命・FWD富士生命・オリックス生命といった金融機関、横浜市・品川区・荒川区・平塚市・川崎市といった行政機関、そしてパートナーの専門家のみなさんとともに、様々なアプローチ方法を考え、ツールを開発してきました。どうすれば経営者に納得した上で事業承継への取り組みに着手していただけるのか?どうすれば途中で頓挫することなく、事業承継を着実にやりとげ、後継者が安心して経営できる環境を実現できるのか?ケーススタディは実に2000件超。失敗もたくさんしてきました。
私たちは、その膨大なケーススタディを通じて、事業承継を効果的に確実に遂行するための一番の秘訣は、事業承継計画書とそれを作成するプロセス(手順)であるという一つの結論を導き出しました。そして、そのノウハウ・フォーマットを整理・体系化し、一まとめにしたのが、事業承継計画書作成講座なのです。
口をきけばケンカをしていた親子が、冷静に会社について
話し合うことができました。事業承継計画書を使って。
ネットで「事業承継計画書」というキーワードを検索して出てくるのは、中小企業庁『事業承継ガイドライン20問20答』に掲載されている、10年間の事業計画を表にまとめる計画一覧表か、それをベースに大手コンサル会社や会計事務所が補足説明をしている程度のものばかりです。しかしながらこの10年間の計画一覧表だけでは、ほとんどの事業承継は上手く進みません。
なぜなら、事業承継に取り組む企業の状況は百社百様であり、それだけで解決するほど単純ではないからです。
特に、現経営者と後継者のコミュニケーションは一筋縄ではいきません。親子であれば長年蓄積した感情のもつれが、従業員承継であれば、社長と社員という長い期間をかけて染みこんだ上下関係が、素直に思ったことを伝える障壁になるからです。感情的な要素は事業承継にとって重要であるにもかかわらず、客観的に整理することが難しいテーマです。事業承継計画書作成講座では、その難しい感情を自然な形で「見える化」し、円滑なコミュニケーションを実現するツールを提供、その使い方をお伝えします。経営者・後継者の胸の中にある思いや長年にわたって築き上げてきたノウハウを「文字に残してあげる」ことが大切なのだと気づかされたことから、このツールが生まれました。こんなことから、私たちは
事業承継計画書は、コミュニケーションツールである
と考えていますので、経営者の想い、後継者の決意を交換して、それぞれの考えていることを擦り合わせ、議論をぶつけていく過程において、本当の事業承継計画書が作られていきます。作って終わりではなく、毎月・毎年見直しながら、社長交代に向かって、課題を解決し、書類を整え、交渉をし、手続きを行っていきます。こうすることで、利害関係者のコミュニケーションを促進し、周りを巻き込んでいくことが出来るのです。事実、この事業承継計画書を使って支援したお客様からは、以下の様なお言葉をいただいています。
「どこから手を付けたらいいかわからないかったけど、あなたのおかげで事業承継が進んだよ」
「先生の言うとおり長男に会社を引き継ぐ日を決めて家族会議を開いたら、家族から了解を得られたよ」
「事業承継計画書」を作ることで信頼を勝ち取った後は、その過程で明らかになった課題を解決する役割をコンサルティング受注することも可能となります。実際に、「後継者の家庭教師をやってほしい」「幹部候補をまとめて教育してほしい」「株式移転の手続きをお願いしたい」「経営承継円滑化法の申請をしてほしい」「退職金積立てのための保険を検討したい」「設備投資(新規事業)に備えて融資を検討したい」と言われる機会もよくあります。なぜなら
事業承継計画書には、経営者に行動を起こさせ、後継者に決意させ、具体的な行動を促す仕掛けが組み込まれているから
事業承継計画書には、後継者の肩書き、株式移転、教育予算を書き込む欄があります。経営者と後継者の考え方、想いを書き込むことで自動的に申請書の一部が作成されるソフトが組み込まれています。さらに、退職金支給・設備投資のキャッシュフロー表も組み込まれています。つまり、この事業承継計画書は、後継者教育計画にもなり、行政への申請書にもなり、金融機関への提出書類にもなるのです。そして、一度作成を手伝った皆様に、再び相談・依頼が来る仕掛けが組み込まれているのです。













この講座でお渡しする事業承継計画書書式ファイルと、実際の案件での活用方法を学べば、具体的な企業の事業承継への取り組みに着手し、進める事ができるようになるでしょう。それも1年や2年もかかるような気の遠くなるものではありません。
事業承継は待ったなしだと考えているのであれば、これほど役に立つツールはないでしょう。事業承継専門のコンサルティング会社が、実際に実務の現場で使っている事業承継計画書書式ファイル、そしてその具体的な活用方法を学ぶ1日の投資にかかる金額の詳細はこちらです。

事業承継センター株式会社 代表取締役
事業承継士/事業承継プランナー 中小企業診断士・CFP
2011年事業承継センター株式会社の設立に参画する。「事業承継士資格取得講座」においてメイン講師を務め、全国に事業承継士を輩出。プロフェッショナル専門家に向けて常に最新の手法、情報、実例を提供するパイオニアである。著書に「いちばん優しい事業承継の本」がある。 ベンチャーキャピタル、コンサルティング会社を経て、33歳で独立。資金調達、銀行交渉、財務ファイナンスを専門としながら「事業承継支援」をライフワークにし、会社法/民法といった法務、金融/保証面の信用、株式/経営権といった権利、土地/建物といった財務の多方面から事業承継におけるテクニカル面をトータルサポートしている。

一般社団法人事業承継協会 代表理事
事業承継士/事業承継プランナー 中小企業診断士
業界初となる「事業承継ノート」「後継者ノート」の発刊、税金や法律の話をあえてしない「いちばん優しい事業承継セミナー」など業界のパイオニア的存在。 出版社での勤務経験があり人間観察力が鋭い。ベンチャー企業の取締役として、成長発展から縮小リストラを経験した強みを活かし、単なる事業承継・相続相談にとどまらず、家族会議への参加や、親子間の人間関係調整も行う。相談者の心に寄り添うコンサルティングには根強いファンがいる。事業承継と相続の専門コンサルタントとして、年間数百件の相談を受ける。また、事業承継の専門家の教育者として金融機関や組織内部の研修実績も豊富で、全国からの依頼も多い。

事業承継センター株式会社 常務取締役
事業承継士/事業承継プランナー 中小企業診断士(平成26年度 中小企業庁長官賞)
後継者塾塾頭を務め、数多くの卒業生の輩出をしている。 損害保険会社の営業として16年間勤務の経験を活かした「売れる仕組みづくり」「売れる営業体制づくり」のためのコンサルティングが得意。事業承継においては、後継者に向けた営業支援はもちろんのこと、経営ノウハウを引き継ぐための「経営の仕組み化」「経営の見える化」を、独自のツールを用いながらサポートしている。著書に「3ヶ月で結果が出る18の営業ツール」がある。平成26年度中小企業診断士シンポジウムにて「サービス業に『再現性』と『創造性』をもたらす科学的メソッド」が、中小企業庁長官賞を受賞。

中小企業診断士・事業承継士
味の素株式会社で営業・労働組合・商品企画・広報・人事と幅広く経験し2019年に中小企業診断士試験合格、2020年5月登録のあと、2020年の6月に1年後の独立開業を目指して早期退職しました。中小企業診断士として独立するにあたり、得意分野を持ちたいと思って事業承継士の資格を取りました。受講者に会計士や弁護士など、他の士業がいてネットワークを作れると言うのも魅力でした。中小企業診断士の資格試験で例えると、事業承継士は理論を中心とした資格試験、事業承継計画書作成講座は実践的な実務補習の位置づけと理解しています。受講してみて、テキストに出てこないような、講師の石井先生による「この項目のヒアリングは、こう言う聞き方をしたら上手くいきやすいですよ」という要所要所での実務に根ざしたワンポイントアドバイスが非常に参考になりました。時間がたったら再度受講してもいいかなと考えています。

中小企業診断士・事業承継士
千葉県産業振興センター事業承継プロジェクトマネージャー
損害保険会社の営業職から、アナウンススクールに通って関西のラジオのお天気お姉さん、イベントの司会業、地ビールの資格(ビアテイスター)を活かした地ビール業界の取材・執筆の仕事をした後、コミュニケーションに関する研修講師の仕事をしていましたが、以前取得していた中小企業診断士の資格を活かして独立したいと思って恩師に相談したところ、事業承継士を勧められ受講しました。事業承継士を取得してすぐ、同じ事業承継士の仲間から、現職の紹介をいただき、これはすぐに勉強が必要だということで、報告を兼ねて金子社長に相談したときに、本講座を勧めてくださり、その時のおすすめポイントが心に刺さり受講を決めました。その時いただいたコメントは、次のとおりです「プロジェクトマネージャーの立場にふさわしいものが、事業承継計画書作成講座です。時系列的に事業承継を俯瞰して、必要なタイミングで専門家をあてがったり、情報を提供したりしながら、多数の案件を管理していくのに最適だと思います」受講してみて、テキストにも「経営者と後継者をつなぐ」「経営者と後継者をつなぐ大切な文章」こういう言葉って、ビジネスの資格とか勉強の講座で、大きく表立って出てこないことだなと感じます。これがあるからこその事業承継計画書。ここがあるなしで、随分変わってくるのではないかと感じました。石井先生がおっしゃってくださる事例も、経営者の方、後継者の方を大事に考えていらして、その会社の大事なものを、本当にいかに聞き漏らさずに、頭の中だけに有ってご本人はあたり前だと思っているけど、それは本当に宝なんですよっていうことをいかに引っ張ってくるか、事例のお話しを伺ってても都度都度出てきて、本当に受けて良かったと思いました。とくに、後継者の本音を引き出すというのは、他の講座やテキストにはないものだと思います。事業承継の支援をやってみて、聞く耳を持ってもらうのが難しいなとか、経営者と後継者の関係性を見ていて、コミュニケーション難しそうだな、とか、コミュニケーションに困難を感じている人にはお勧めです。

株式会社エスアンドエスネットワーク
代表取締役社長
経営コンサルタント・事業承継士
長いお付き合いをさせて頂いているお客様が多く、50代60代の社長様が増えてきて事業承継の話題が増えてくるようになった事もあり、当社としても事業承継をクローズアップして取り組みたいと思っておりました。そこでWeb等で情報収集をしたところ、貴社の事業承継士という資格を見つけ、早速オンラインガイダンスに参加しましたが、正直なところ迷っていました。その時、ちょうどお客様から事業承継について具体的に相談に乗って欲しいという話があった事が後押しになり、ここで一度体系的に学び直し、自分の中で整理しておくのも良い機会だと思って事業承継士資格取得講座を受講しました。
事業承継計画書作成講座は、事業承継士資格取得後の事務局からのメールマガジンで存在を知りました。実は受講前は、単なる計画表の作成講座だと思っていたのですが、実際に受講してみると、計画表づくりはほんの一部に過ぎず、承継の段取りそのものであって、経営者と後継者の意識のすり合わせの進め方、特に経営者(もちろん後継者も)が覚悟を決めることや、そこに導くプロセス等が含まれており、とても広い領域を扱う内容だったので、良い意味で期待を裏切られました。(計画書作成というよりは、ソフト面の承継の段取りに近いのかなと感じました。)
事業承継を仕事にしていくと覚悟した方であれば、一回は受けてみて良いと思います。

Hopeful Future株式会社(ホープフルフューチャー株式会社)
代表取締役
事業承継士
上級BCP診断士(一般社団法人日本BCP協会)
一般社団法人日本BCP協会認定インストラクター
2021年度MDRT成績資格会員/Court of the Table
2025年問題等、法人の勉強をしているときに、テーマとして事業承継は必須と思い実務のスキルをもっと上げたいと思っていたところ、地元の商工会議所の税理士(事業承継士)さんに教えていただいて事業承継士資格取得講座を受講しました。もっとお客様のお役に立ちたいという思いで、事業承継計画書作成講座も事業承継士の後すぐに申し込みました。お客様先の事業承継が、スピード感がゆっくりで進まなくて悩んでいたのですが、事業承継士資格取得講座を受けて、「あ、こんなお役の立ち方があるんだ」「とりあえず事業承継計画を作ってみよう」という風に考えればよくなりました。本人のやる気がないと進まないなということも再確認できたので、今はバトンを渡す現経営者ご本人の同意を少しずつ得られるように動いています。事業承継計画書作成講座は、お客様で事業承継計画をつくる必要性に迫られて、いい機会だなと思って受けました。以前、別件で事業承継をしなければならないとなったとき、自分なりに事業承継計画書を作って、その時にいろいろやってみたのですが、体系的にもっと細かく、ブラッシュアップして行きたいと思っていたのもあります。
実際に事業承継計画書作成講座を受けて、しっかりと体系だった原点に立ち返り確認ができるものができたのはすごく助かります。
講義の中で、事業承継計画書を作ることが目的にならない様に、本質的なところ(綺麗事じゃないところ)、大事にすべき所の話しがあったので、我流でやっていて不安な方、本質的に深く理解したい人は受けた方がいいと思います。