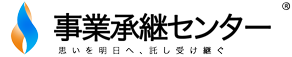いよいよ経営承継円滑化法の特例措置の締め切りが近づいてきました。2026年3月末までに、特例承継計画を提出して認定してもらうことで、2027年12月末までに贈与または相続(実際は贈与となる。先代社長の死亡時期は特定できないため)すれば、発行済株式数の100%分すべての贈与税が納税猶予されるというのは、このメルマガで何度も解説してきた通りです。
では、どれくらい納税がお得になるのか?というシミュレーションをしてみましょう。
ここに、都内某所にある下請けの製造業を想定してみます。年商3億円で経常利益は毎期1000~2000万円を計上している中小企業です。自社所有の不動産が値上がっているため、自社株式の評価額は20万円 になっていました。発行済株式総数は 1,000株で、すべて現経営者(70歳)が保有していますので、総額2億円となります。後継者(40歳)は立派に育ち、来年2026年6月の株主総会で社長交代をする予定です。また、この自社株式以外の相続財産として不動産1億円と現金5000万円があるものとし、奥様は亡くなってしまったため、法定相続人は後継者である長男とサラリーマンの次男とします。
① 贈与時(2026年6月)の贈与税
• 贈与財産 2億円 − 基礎控除110万円 = 1億9,890万円
• 贈与税額 = 198,900,000 × 55% − 6,400,000 = 102,995,000円
• 特例措置:全額猶予
※結論として、102,995,000円が全額納税猶予されますので、贈与税は1円もかからず、先代経営者の株式100%を後継者に贈与することが出来ました。
次に、この後継者が頑張って経営に専念した結果、株価が20⇒25万円に上昇した10年後に先代経営者が亡くなった時はどうなるのでしょうか?実は、経営承継円滑化法では贈与時の株価で相続財産を固定して計算してよい、となっているため後継者の頑張り分が損にはならないように設計されているところがポイントです。
② 贈与者死亡(10年後)の相続税
相続財産
• 株式(贈与時価額で固定されるため2億5000万円ではなく⇒):2億円
• 不動産:1億円
• 現金:5,000万円
• 合計:3億5,000万円
相続税の基礎控除
• 3,000万円 + 600万円 × 相続人2人 = 4,200万円
課税遺産総額
• 3億5,000万円 − 4,200万円 = 3億800万円
法定相続分による分割
• 相続人:長男・次男 → 各1/2
• 各自の課税取得金額:3億800万円 ÷ 2 = 1億5,400万円
各人の相続税(速算表)
• 1億5,400万円 × 40% − 1,700万円 = 4,460万円
相続税総額
• 4,460万円 × 2人 = 8,920万円
③ 納税猶予の切替額
• 特例措置
o 株式部分(2億円)に対応する相続税を試算する。
o 仮に株式2億円だけを相続財産とすると:
課税遺産総額 = 2億 − 4,200万 = 1億5,800万
法定相続分 = 7,900万円ずつ
各自の相続税 = 7,900万 × 30% − 700万 = 1,670万
相続税総額(株式部分) = 3,340万円
o 特例措置は100%猶予 → 3,340万円が猶予
o 実際の納税 = 総相続税8,920万 − 猶予3,340万 = 5,580万円
※上記の通り納税額は5,580万円となりますが、特例措置の猶予対象者は株式を承継した長男です。よって、株式部分の相続税 3,340万は長男に発生するはずの税ですが 全額猶予されます。一方で不動産1億円と現金5,000万円を相続するのは次男なので、この部分の相続税5,580万円は次男が納付することになります。
つまり、相続時でも特例措置を使えば贈与時と同じく長男に関しては1円も相続税を納税する必要がないということになります。
確かに贈与税は相続税に比べて割高なので、「相続まで自社株式移転を待って、相続税で解決すればいい」という専門家もおり、そうした選択もありでしょう。ただし、果たして自社株式が100%後継者に確実に相続されるのか?という観点を忘れてはなりません。遺言があるならまだしも、遺産分割協議で揉めでもしたら、株式の一部を次男が所有することになる可能性も否定できません。それに相続税は贈与税に比べて低い税率だとはいうものの、3,340万円(本来は株価上昇も加味しなければならないため5,575万円)も納税しなければならないのを0円にすることが可能なのです。
もちろん、すべてのケースで経営承継円滑化法を使った方がいいわけではなく、ケースバイケースの対応にはなりますが、純資産で1億円以上ある会社は、経営承継円滑化法を検討し、特例承継計画を活用できるラストチャンスにかけてみるというのはありなのです。
ここまでお話しても、まだすっきりしない方には、参考までに2024年1月から改正された 相続時精算課税制度 を利用した場合をシミュレーションしてみましょう。この制度では、選択後に暦年課税に戻すことはできませんが、毎年110万円までの贈与は申告不要かつ相続時に持ち戻し不要となりました。従来よりも柔軟に利用できる制度になっています。
今回のケースでは、
• 2026年6月に株式2,500万円分を相続時精算課税制度で贈与(非課税ぎりぎり)
• その後10年間、毎年110万円ずつ株式を贈与(計1,100万円、非課税)
• 残りの株式1億6,400万円を、相続時(株価25万円)に評価すると2億500万円
となります。
相続財産の内訳(贈与持戻し後)
• 株式:2億500万円(長男が相続)
• 不動産:1億円(次男が相続)
• 現金:5,000万円(次男が相続)
• 合計:3億5,500万円
相続税計算
基礎控除:3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円
課税遺産総額:3億5,500万 − 4,200万 = 3億1,300万円
法定相続分による分割
• 相続人:長男・次男 → 各1/2
• 各自の課税取得金額:3億1,300万円 ÷ 2 = 1億5,650万円
各人の相続税(速算表)
• 1億5,650万円 × 40% − 1,700万円 = 4,560万円
相続税総額
• 4,560万円 × 2人 = 9,120万円
各人の相続税額は、相続した財産価格で割り振るため、
① 長男分→9,120万円×2億500万円/(2億500万円+1億円+5,000万円)≒5,266万円(端数切捨て)
② 次男分→9,120万円×(1億円+5,000万円)/(2億500万円+1億円+5,000万円)≒3,853万円(端数切捨て)
このように見ますと、やはり後継者である長男は、相続時精算課税を使ったとしても5,266万円の納税をする必要があるため、圧倒的に経営承継円滑化法を活用した方が有利だということがわかります。ここで、興味深いのは、次男についていえば、逆に3,853万円から5,580万円へと納税負担が大きくなっていることでしょう。この点については、何か別の並行財産を用意してあげるなどして兄弟間のバランスを取るなど工夫が必要だとは思われます。しかしながら、兄弟トータルの納税額という観点からは圧倒的に有利になるということはお分かり頂けたのではないでしょうか?
Writer:金子 一徳