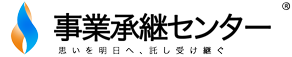いよいよ「経営承継円滑化法」に基づく特例措置の締め切りが近づいてきました。
皆さまの顧問先や取引先には、しっかりと情報共有ができているでしょうか。
「どうせまた延長されるのでは?」「10年間の特例が恒久化されるらしい」といった噂も一部で聞かれますが、実際にはそのような確証はありません。
むしろ中小企業庁では、2025年8月に公表された『中小企業の親族内承継に関する検討会 中間とりまとめ』のなかで、特例措置終了を見据えた制度見直しの議論が進められています。
その要点を整理すると、次のようにまとめられます。
① 一般措置の納税猶予対象株式が3分の2に制限されている点(特例措置は100%)
→ この上限が制度活用の大きなハードルになっているのではないか。
② 一般措置では贈与は100%猶予される一方、相続は80%にとどまる点(特例措置は贈与・相続とも100%)
→ 後継者の負担感を高め、制度の一体性を損なっているのではないか。
③ 納税猶予という仕組み自体が「永続的な負担」を生むこと
→ 一定期間(例えば10年間)継続的に経営すれば免除に転じるような仕組みが検討できないか。
④ 雇用の5年間・8割維持要件が現実と乖離している点
→ 人手不足や賃上げ圧力の中で、給与水準の上昇など他の要素を考慮すべきではないか。
これらは、制度の理念と現場の実態のギャップを埋めるための重要な論点です。
そして、事業承継協会としての見立てを加えると——
特例措置は予定通り2027年12月末で終了し、その後は「一般措置」が改正・拡充される方向で議論が進む可能性が高い。
ということです。
つまり、特例措置の活用を検討しつつも、今後は「改正後の一般措置」が実質的に同等か、あるいはそれ以上に使いやすい制度として生まれ変わることが期待されます。
特例の申請期限まであとわずか。今こそ顧客への周知と並行して、「一般措置への移行」を見据えた体制整備が求められます。
単なる延長待ちではなく、制度の本質を理解した“次の一手”を、早めに打っておくべき時期に来ているといえるでしょう。
Writer:金子 一徳